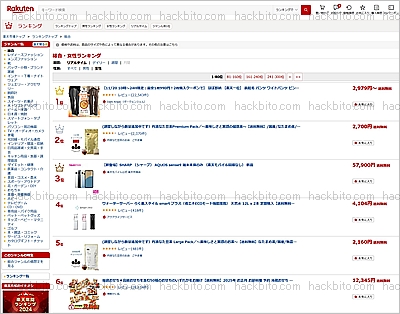共働き家庭にとって、子どもの放課後を
安心して任せられる学童保育はまさに生活の要です。
学童保育を必要とする理由を整理し、
家庭ごとのリアルな背景に寄り添いながら、
豊富な例文とポイントで丁寧に解説します。
本記事は、実際の申請書や志望動機にも使いやすい構成を心がけ、
さまざまな状況に応じた考え方を
わかりやすくまとめました。
紹介する具体例を読むことで、
自分にぴったりの言葉選びが見えてきます。
ぜひ最後までご覧ください。
- 共働き家庭が学童保育を必要とする理由【例文と志望動機にも使える書き方を解説】
- 学童保育を必要とする理由の書き方と例文|保育支援が必要な家庭の状況別に解説
- 就労証明で伝える理由の具体的な記載例【フルタイム・パート・在宅勤務】
- 申請書・履歴書に活用できる例文|共働き世帯・家庭の事情を効果的に伝える方法
- 祖父母に頼れない・子育て支援が難しい家庭向けの理由例文
- ひとり親・シングル家庭が安心して学童保育を利用するための理由例文
- 学童保育の申請書・志望動機の書き方と注意点
- 共働き世帯が学童保育を利用する背景と社会的課題
- 小1の壁と放課後時間の両立|子どもの生活と保護者の勤務の現実
- 共働きでも入れない?学童保育の待機児童問題と対応策
- 民間学童と公立児童クラブの違い|施設の条件や役割を比較
- 利用時間・送迎体制・保護者の負担の違いとは
共働き家庭が学童保育を必要とする理由【例文と志望動機にも使える書き方を解説】
共働き家庭が学童保育を必要とする理由は、 子どもが安心して過ごせる環境を確保し、 保護者が安定して働き続けられる状況を支えるためです。
特に、就労時間が小学校の下校時刻よりも遅い場合、 放課後の子どもの居場所に困る家庭が多くあります。 このような状況で学童保育は、 保育の役割を果たす重要な支援となります。
また、共働きで親がそろって家を空ける時間が長い場合、 子どもが一人で留守番をする時間が増えてしまいます。 それにより、不安や孤独を感じることもあります。 学童保育では、スタッフの見守りのもとで 宿題をしたり、友達と遊んだりすることができ、 日常的な生活の流れを安定させる役割も担っています。
学童保育を必要とする理由として、 保護者の勤務形態や勤務先の距離、 兄弟姉妹の年齢構成など、 家庭ごとの事情も挙げられます。
以下に、申請書や志望動機の例文として活用できる 書き方の一例をいくつか紹介します。
「私たちは共働き家庭で、 いずれも平日は午後6時以降まで就労しております。 子どもの下校後、家庭で一人になる時間が長く、 安心して過ごせる場所が必要です。 学童保育を通じて、生活リズムを保ち、 社会的な関わりを持てるよう支援をお願いしたく、 申請させていただきます。」
「夫婦ともにフルタイム勤務のため、 子どもの下校時間に合わせた在宅が難しい状況です。 子どもが安心して過ごせる場所として、 学童保育の利用を希望しております。」
「現在、夫婦ともに電車通勤をしており、 帰宅が午後7時頃になります。 子どもがひとりで過ごす時間が長く、 安全面を考慮し、学童保育の利用を希望しております。」
「下の子の保育園の送迎と、上の子の下校時刻が重なるため、 上の子の居場所を確保する必要があります。 共働きで時間のやりくりが難しい中、 学童保育の支援をお願いしたく申請いたします。」
「共働きで家を空ける時間が長く、 子どもが孤立しないよう、学童保育での集団生活を通して 他の子どもたちとの関わりを大切にしたいと考えております。」
このように具体的な状況を簡潔に述べることで、 「なぜ学童保育が必要なのか」を 相手に伝えやすくなります。 単に”共働き”という理由だけでなく、 その家庭の事情を丁寧に説明することが大切です。
【共働き家庭が学童保育を必要とする主な理由を書く際のポイント】
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 下校後の居場所がない | 就労時間と下校時間が合わず、自宅で過ごせない |
| 長時間の留守番が心配 | 子どもが一人になる時間を減らしたい |
| 安定した生活リズムの確保 | 宿題・遊び・見守りがあり、安心して過ごせる |
| 就労の継続が必要 | 両親ともに働くため、保育支援が不可欠 |
| 家庭の事情による申請が必要 | 兄弟構成や通勤距離など、個別の事情に合わせた申請理由が必要 |
学童保育を必要とする理由の書き方と例文|保育支援が必要な家庭の状況別に解説
学童保育を必要とする理由は、家庭ごとの状況や
保育支援の必要性によってさまざまです。
特に共働き家庭やひとり親家庭では、
放課後の子どもの預け先として
学童保育の役割が重要になっています。
ここでは、そうした背景をふまえたうえで、
学童保育を必要とする理由の書き方や、
状況別に使える例文について整理しています。
就労証明で伝える理由の具体的な記載例【フルタイム・パート・在宅勤務】
就労証明で伝える理由は、学童保育を必要とする理由として、共働き家庭の実情に沿った記載が求められます。 特にフルタイム勤務、パート勤務、在宅勤務の働き方ごとに、具体的な表現が異なるため、状況に応じた適切な例文を用意しておくことが大切です。
■ 例文①:フルタイム勤務(共働き)
夫婦ともに週5日、9時〜18時のフルタイム勤務をしており、
子どもが帰宅する時間には誰も在宅できません。
学童保育を利用することで、放課後の居場所を確保したいと考えています。
■ 例文②:通勤に時間がかかる共働き世帯
共働きでそれぞれ片道1時間以上の通勤時間があり、
下校時に対応できる家庭内支援がありません。
子どもを安心して過ごさせるために、学童保育を必要としています。
■ 例文③:パート勤務だが扶養内フル稼働
週5日、1日5時間のパート勤務をしています。
扶養内勤務ではあるものの、下校時間と勤務時間が重なるため、
共働き家庭として学童保育の支援が必要です。
■ 例文④:在宅勤務だが業務に集中が必要
在宅勤務が中心ですが、
オンライン会議や納期前の業務が多く、育児との両立が困難です。
共働きで、業務に集中できる環境確保のために学童保育を利用したいと考えています。
■ 例文⑤:不定期シフト制勤務
夫婦ともに不定期なシフト勤務のため、
日によって帰宅時間や出勤時間が変動します。
放課後の子どもの見守り体制が整えられず、
安定した学童保育の利用が不可欠です。
■ 例文⑥:短時間勤務でも預け先が必要
現在、週4日、9時~13時までの短時間勤務をしています。
下校が早い曜日や長期休暇中などは、自宅での対応が難しいため、
学童保育の利用が必要と判断しています。
■ 例文⑦:週末勤務のある職種
平日と土日を含めた交代勤務の職種に就いており、
学童保育を活用することで家庭内の育児環境を整えたいと考えています。
共働き世帯として柔軟な預け先が求められています。
■ 例文⑧:在宅と出社の混合勤務
週3日は在宅、週2日は出社という勤務体制で働いています。
在宅時も業務に集中する必要があり、出社日には通勤時間も含めて育児が難しいため、
安定して利用できる学童保育を必要としています。
■ 例文⑨:看護師など夜勤を含む勤務
夫婦ともに病院勤務で、夜勤・早番・遅番など不規則な勤務が含まれます。
家庭内での育児対応が難しいため、子どもの放課後を支える学童保育の利用が必要です。
■ 例文⑩:自営業・フリーランス
自宅を拠点にフリーランスで働いていますが、
業務中は集中が求められるほか、外出取材や打ち合わせもあります。
共働きの状況とあわせて、学童保育の利用が欠かせません。
| 例文番号 | 働き方の種類 | 就労証明に記載すべき内容 | 学童保育を必要とする理由 |
|---|---|---|---|
| ① | フルタイム勤務 | 勤務時間と共働き状況 | 放課後の見守り不可 |
| ② | 長距離通勤 | 通勤時間・支援なし | 対応が難しい |
| ③ | パート勤務 | 短時間でも重なる時間あり | 留守番させられない |
| ④ | 在宅勤務 | 会議・業務集中あり | 家での見守りが困難 |
| ⑤ | シフト制勤務 | 勤務時間が日ごとに異なる | 安定した預け先が必要 |
| ⑥ | 短時間勤務 | 長期休暇・早帰りの対応困難 | 柔軟な支援が必要 |
| ⑦ | 週末勤務あり | 土日出勤がある | 家族で分担できない |
| ⑧ | 混合勤務 | 在宅と出社の両方あり | 日によって必要性が変動 |
| ⑨ | 夜勤あり | 勤務が不規則 | 夜間や夕方の育児が難しい |
| ⑩ | フリーランス | 外出・打ち合わせあり | 育児との両立が難しい |
申請書・履歴書に活用できる例文|共働き世帯・家庭の事情を効果的に伝える方法
申請書や履歴書に「学童保育を必要とする理由」を記載する際は、 共働きである家庭の事情をわかりやすく伝えることが大切です。 具体的な生活状況や保育の必要性を明確にすることで、 審査担当者に理解してもらいやすくなります。
以下に、共働き世帯が学童保育を希望する理由として使える例文を紹介します。 申請書にも履歴書にも活用できるよう、 簡潔で伝わりやすい表現にまとめました。
■ 例文①:共働きフルタイム家庭
夫婦ともに平日9時から18時までフルタイム勤務しており、
帰宅は19時近くになります。
放課後に子どもを安心して預ける環境が必要なため、
学童保育の利用を希望します。
■ 例文②:長時間通勤による育児困難
共働きで通勤時間が片道1時間以上かかるため、
小学校の下校時に子どもを迎えることができません。
子どもの安全と生活リズムを守るために、
学童保育を必要としています。
■ 例文③:在宅勤務だが育児との両立が困難
在宅勤務ではありますが、
オンライン会議や資料作成など集中が必要な業務が多く、
子どもの見守りが難しい状況です。
共働き家庭として、学童保育の支援が不可欠です。
■ 例文④:早朝勤務+日勤の組み合わせ
私は早朝勤務、夫は通常の9時〜18時勤務で働いており、
家庭内で放課後の保育ができる体制がありません。
学童保育を利用し、生活の安定を図りたいと考えています。
■ 例文⑤:シフト制勤務による不規則な生活
共働きで、日によって勤務時間が変わるシフト制勤務です。
子どもが一人で帰宅して過ごす時間帯が発生するため、
学童保育を必要としています。
■ 例文⑥:実家が遠方で頼れる支援がない
共働きですが、実家が遠方にあるため祖父母の支援を受けられません。
日常的な預け先が確保できず、
放課後の子どもの居場所として学童保育が必要です。
■ 例文⑦:共働き+下の子の送迎対応が難しい
夫婦ともに働いており、
下の子の保育園送迎などで平日の時間が限られています。
上の子を安心して預けられる学童保育の利用を希望します。
■ 例文⑧:子どもが低学年で留守番に不安がある
共働きで、子どもがまだ小学1年生と幼く、
自宅での留守番には大きな不安があります。
見守り体制が整った学童保育にお願いしたいと考えています。
■ 例文⑨:子どもが友達と過ごせる環境を求めて
共働きで帰宅時間が遅いため、
子どもが放課後を孤独に過ごすことになります。
学童保育を利用し、同年代の友達と過ごせる場所を確保したいです。
■ 例文⑩:仕事と家庭のバランスを保つため
共働きのため、仕事と家庭のバランスを保つには、
学童保育のサポートが欠かせません。
安心できる環境で子どもを預かっていただけると助かります。
| 例文番号 | 世帯状況 | 学童保育を必要とする理由 |
|---|---|---|
| ① | 共働きフルタイム | 放課後の預け先が必要 |
| ② | 長距離通勤 | 帰宅までの見守りが不可 |
| ③ | 在宅勤務 | 業務中の育児が困難 |
| ④ | 時間差勤務 | 家庭内で保育ができない |
| ⑤ | シフト勤務 | 時間帯が不規則 |
| ⑥ | 支援なし | 預け先の確保が難しい |
| ⑦ | 下の子の対応あり | 上の子の保育が難しい |
| ⑧ | 低学年の子ども | 留守番が不安 |
| ⑨ | 子どもの交流重視 | 社会性を育みたい |
| ⑩ | 両立支援 | 働き続けるために必要 |
祖父母に頼れない・子育て支援が難しい家庭向けの理由例文
「祖父母に頼れない・子育て支援が難しい家庭向けの理由例文」
学童保育を必要とする理由 共働き 例文として、祖父母に頼れない家庭では
共働きの家庭が、日中の子育て支援を得られない状況に直面しています。
まず、「祖父母に頼れない」点が重要な理由で、都市部や核家族化の影響で
近くに頼れる親族がいないケースが増えています。
さらに、夫婦共にフルタイム勤務やシフト制勤務となると、
育児と仕事の両立が非常に困難になります。
| 例文番号 | 家庭状況 | 祖父母の状況 | 学童保育を必要とする理由 |
|---|---|---|---|
| ① | フルタイム共働き | 遠方在住・支援不可 | 放課後に安心して子どもを預けたい |
| ② | シフト制共働き | 不在・支援なし | 育児の孤立を防ぎ両立を図るため |
| ③ | 在宅勤務 | 不在・頼れない | 業務に集中するための預け先が必要 |
| ④ | 片親・単身育児 | 遠方・不在 | 安心して働くための環境整備が必要 |
| ⑤ | 共働き | 近隣だが高齢・体調不安 | 預け先がなく不安定な状況のため |
| ⑥ | 共働き | 現役でフルタイム勤務 | 祖父母に日中の支援を頼めないため |
| ⑦ | 共働き・転勤あり | 遠方 | 地縁がなく、放課後の対応ができない |
| ⑧ | 共働き | 高齢で負担をかけたくない | 無理な依頼を避けつつ両立したい |
| ⑨ | 子どもが3人以上 | 他の兄弟や介護で手が回らない | 長子の居場所確保が必要 |
| ⑩ | 片親・介護中 | 要介護で支援不可 | 就労継続と育児を両立させるため |
■ 例文①:フルタイム共働き+祖父母サポートなし
夫婦ともに平日8:30~18:00のフルタイム勤務をしており、
実家は遠方で祖父母のサポートを受けられません。
学童保育を活用し、日中の生活リズムを安定させながら、
安心して仕事に専念できる環境を整えたいと考えています。
■ 例文②:シフト制勤務+ワンオペ育児
夫が夜勤を含むシフト勤務、私も日勤の共働きで、
日中に祖父母の助けを得ることができず、育児が孤立状態です。
学童保育を利用することで、子どもの放課後が安定し、
仕事と育児の両立が可能になると考えています。
■ ■ 例文③:在宅勤務でも学童が必要なケース
テレワーク中でもオンライン会議や集中作業が多く、
子どもの世話に対応しづらい時間帯があります。
祖父母に頼れない状況で、学童保育を活用し、
日中に安心して子どもを預けながら業務に専念したいです。
■ 例文④:単親+祖父母不在
片親としてフルタイムで働く中、祖父母は遠方に在住のため頼れません。
学童保育の利用により、子どもが友だちと過ごす場を確保しつつ、
私が安心して働くためのサポート体制を作りたいと考えています。
これらの例文は、以下のポイントを押さえつつ、
「学童保育を必要とする理由 共働き 例文」というキーワードを
見出しや文章中に自然に含めています。
・フルタイムやシフト制勤務など具体的な就労状態
・「祖父母に頼れない」背景の明示
・学童保育を使うことで得られる安心感と両立の必要性
■ 例文⑤:近距離でも高齢・体調不安の祖父母
祖父母は近隣に住んでいますが、
高齢で体調も万全ではなく、日常的な育児支援は頼めない状況です。
共働きで放課後の子どもの過ごし方に不安があるため、
安心して預けられる学童保育の利用を希望します。
■ 例文⑥:祖父母が現役でフルタイム勤務
祖父母は健在ですが、現在も現役でフルタイム勤務しており、
平日の日中は子どもの面倒を見ることができません。
私たち夫婦も共に働いているため、
放課後の時間を安全に過ごせる環境として学童保育を利用したいと考えています。
■ 例文⑦:引っ越しで祖父母と離れて暮らしている
転勤により、実家を離れて現在の居住地に移りました。
祖父母は遠方に住んでおり、
緊急時を含めて日常的に子育てを手伝ってもらうことができません。
共働き家庭として、安心できる学童保育のサポートが必要です。
■ 例文⑧:祖父母に精神的・身体的な負担をかけたくない
祖父母は体調が悪いわけではありませんが、
高齢であり、育児支援をお願いすることに精神的・身体的な負担を感じさせたくないと考えています。
共働き家庭として子どもの居場所を確保するため、
学童保育を選択することが最も現実的だと判断しました。
■ 例文⑨:兄弟が多く、自宅での保育に限界がある
3人の子どもがいて、下の子はまだ未就園児です。
祖父母には他の兄弟の支援や介護もあり、学齢期の長子にまで手が回りません。
共働きの中で、上の子の放課後を安心して任せられる学童保育は、
家庭にとって必要不可欠な存在です。
■ 例文⑩:シングル家庭+祖父母は介護を受ける側
シングルで子どもを育てており、
祖父母は介護が必要な状態のため、逆に私が支援を行う立場です。
日中の子どもの預け先がないと就労が継続できず、
学童保育は生活の安定を保つために欠かせない選択肢です。
ひとり親・シングル家庭が安心して学童保育を利用するための理由例文
ひとり親・シングル家庭が安心して学童保育を利用するための理由例文
ひとり親・シングル家庭では、学童保育を必要とする理由が多岐にわたります。
共働きと同様に、就労と子育てを両立するには、安心できる放課後の預け先が欠かせません。
以下に、実際の申請書や履歴書にも活用できる具体的な例文を紹介します。
■ 例文①:フルタイム勤務のシングルマザー
現在、平日9:00~18:00までフルタイムで働いております。
夫とは離婚しており、子どもを一人で育てています。
放課後に安心して過ごせる場所として、
学童保育の利用を希望いたします。
■ 例文②:祖父母も頼れないひとり親家庭
夫を亡くしてから、子どもと2人で生活しています。
実家は遠方にあり、近くに頼れる親族はいません。
学童保育を利用することで、子どもの生活リズムを保ちつつ、
私自身も安定して仕事を続けることができます。
■ 例文③:夜勤のあるシングルファーザー
夜勤を含む不規則な勤務体制で働いています。
小学校低学年の子どもを一人で家に残すことはできないため、
学童保育の利用が必要です。
「学童保育を必要とする理由 共働き 例文」と同様に、
仕事との両立の観点からも欠かせない支援です。
■ 例文④:就職活動中のひとり親
離婚後、現在は求職中ですが、
面接や研修が入る際に子どもを預ける先が必要です。
就職が決まった後も安定して働くために、
学童保育の登録を希望します。
■ 例文⑤:パート勤務のシングルマザー
昼から夕方にかけてパート勤務をしています。
子どもが一人で留守番するのは不安が大きく、
仕事中の集中にも影響が出てしまいます。
学童保育を利用することで、子どもも私も安心できます。
■ 例文⑥:介護と育児の両立をする母子家庭
要介護の親と同居しており、
育児と介護を両立しながら働いています。
限られた時間の中で、子どもの放課後の居場所を確保するため、
学童保育の支援が不可欠です。
■ 例文⑦:低学年の子がいるシングル家庭
子どもはまだ小学校1年生で、
放課後に一人で過ごすのは心身ともに不安があります。
近くに知人もおらず、学童保育に通わせることで、
安心して働き続けることができます。
■ 例文⑧:扶養手当の支援対象としての申請
児童扶養手当を受給している母子家庭です。
仕事を続けることで生活を安定させるためにも、
学童保育の制度を活用し、子どもの放課後を見守っていただければと思います。
■ 例文⑨:再就職準備中で必要な預け先がない
再就職に向けて職業訓練に通っており、
日中は子どもを見守ることができません。
学童保育を利用できれば、安心してスキルアップに専念でき、
家庭の経済的自立にもつながります。
■ 例文⑩:就労継続が難しいため利用を希望
ひとり親として働きながら育児を続けていますが、
保育や放課後の支援がなければ就労継続が難しい状況です。
学童保育を活用することで、家庭生活と仕事を両立できます。
| 例文番号 | 家庭状況 | 学童保育を必要とする理由 |
|---|---|---|
| ① | フルタイム勤務のシングル | 放課後の預け先が必要 |
| ② | 祖父母不在・頼れない | 日中支援が得られず必要不可欠 |
| ③ | 夜勤あり | 子どもを一人にできない |
| ④ | 就職活動中 | 面接・研修時の預け先が必要 |
| ⑤ | パート勤務中 | 留守番への不安・仕事の集中 |
| ⑥ | 介護と育児の両立 | 二重負担の軽減 |
| ⑦ | 小学1年生の子がいる | 一人で過ごせない年齢 |
| ⑧ | 扶養手当受給世帯 | 経済的に必要な支援 |
| ⑨ | 職業訓練受講中 | 自立のための預け先が必要 |
| ⑩ | 働きながら育児 | 働き続けるために必須の制度 |
学童保育の申請書・志望動機の書き方と注意点
学童保育の申請書や志望動機の作成にあたっては、
伝えるべき内容や言葉の選び方に工夫が必要です。
共働き家庭であることを前提にしても、
ただ状況を記載するだけでは思いが伝わりづらくなります。
ここでは、申請書と志望動機を書く際の
具体的なポイントと注意点を整理しながら、
内容をわかりやすくまとめていきます。
学童保育の申請書で伝えるべき内容とは?
学童保育の申請書では、まず「なぜ学童保育を必要とするのか」という理由を明確に書くことが大切です。
たとえば、保護者がフルタイムで働いており、放課後に家庭で子どもの面倒を見ることが難しいという事情が典型的です。
具体的には次のような要素を盛り込みましょう。
-
就労状況:勤務日数や時間、通勤時間などを簡潔に記載し、放課後の保育が必要である根拠を伝えます。
-
家庭の状況:祖父母などのサポートが受けられない、きょうだいの育児と両立が難しいなど、具体的な事情を添えると説得力が増します。
-
子どもの様子:一人で留守番をさせるのが難しい年齢であることや、集団生活を通して成長を促したいという思いも伝えると、配慮ある内容になります。
申請書は事実をもとに、簡潔かつ丁寧にまとめることがポイントです。感情的になりすぎず、客観的な情報を中心に書くようにしましょう。
志望動機の書き方と構成のコツ
志望動機を書く際は、単に「働きたい」ではなく、なぜこの施設で働きたいのかを明確にすることが重要です。
以下の構成を参考にすると、読み手に伝わる志望動機になります。
-
きっかけ
例:「自分自身も共働きの家庭で育ち、学童保育に支えられてきた経験があるため」 -
関心・共感
例:「〇〇学童保育が子どもたちの自主性を大切にしている点に共感しました」 -
経験・スキル
例:「保育補助として3年間勤務し、児童の放課後活動支援に携わってきました」 -
意欲と将来の関わり方
例:「共働き家庭の支援に貢献したいという思いを持ち、日々安心して子どもが通える場づくりをしたいです」
このように段階的に構成することで、読みやすく説得力のある志望動機になります。
志望動機・申請書でよくある注意点と対策
学童保育の申請書や志望動機でありがちなミスも知っておくと、失敗を避けることができます。以下に注意点をまとめます。
-
抽象的な表現は避ける
「子どもが好き」「貢献したい」などの抽象的な言葉だけでは不十分です。理由や具体的なエピソードを添えると説得力が高まります。 -
待遇や条件を前面に出さない
「土日休みだから」「家から近い」など、自分本位に見える理由は避けましょう。あくまで子どもや保護者、学童の理念に寄り添う姿勢が大切です。 -
使い回しの文章に見えないようにする
ネットでよく見かけるテンプレートをそのまま使用すると、個性が出にくくなります。オリジナルの経験や気持ちを織り交ぜて、唯一無二の文章にしましょう。
共働き世帯が学童保育を利用する背景と社会的課題
共働き世帯が学童保育を必要とする理由には、子どもの放課後や長期休暇中に預け先がない状況が背景にあります。詳細をみていきます。
■背景|共働き世帯の増加と家庭環境の変化
近年、共働き世帯の割合は年々増加しており、2023年の厚生労働省の調査によると、共働き世帯は専業主婦世帯の約2倍以上にのぼっています。
この背景には、女性の社会進出やライフスタイルの多様化、経済的な必要性などがあり、子育てと仕事を両立する家庭が主流になりつつあります。
また、核家族化の進行により、祖父母や親戚などに子どもを預けるといった選択肢が取りづらくなってきました。
その結果、小学生の放課後や長期休暇中に子どもの居場所がなくなり、学童保育を必要とする家庭が増えています。
■ニーズ|放課後や長期休暇中の預け先確保が困難に
多くの共働き家庭では、保育園卒園後の「小1の壁」に直面します。
これは、学校の終了時間が早いため、親の就労時間と合わず、子どもの居場所がなくなる問題を指します。
さらに、夏休みや冬休みなどの長期休暇になると、1日中子どもの面倒を見る必要があり、会社を休むか、有償の預かりサービスを利用せざるを得なくなります。
このように、放課後や休暇中に子どもを安心して預けられる場所が限られているため、学童保育へのニーズは非常に高くなっているのです。
■現状|待機児童問題と地域による偏在
2024年現在、全国の学童保育(放課後児童クラブ)の利用希望者のうち、約1万7千人が待機状態にあります。
特に都市部では、施設数や定員が追いついておらず、空きがないために入所できないケースが目立ちます。
一方、地方では空きがあるにもかかわらず、アクセスが悪かったりサービスの質が不安定で利用が進まないという地域格差も課題です。
このような状況は、保護者にとって大きな不安材料となっており、仕事を続ける上での妨げになっています。
■支援員課題|労働条件が不安定で人材確保が困難
学童保育を支える「放課後児童支援員」の処遇も深刻な問題です。
多くの支援員は非常勤で雇用されており、時給も低めに設定されていることが多いため、安定した生活を維持するのが難しい現状があります。
また、長時間の預かりや保護者対応、子どものトラブル対応など、責任の重さに対して報酬が見合っていないとの声も多く、離職率が高いことが課題です。
結果として、支援員不足が起き、子ども一人ひとりにきめ細かい支援が届かないという悪循環を生んでいます。
■社会的課題|制度整備・支援体制の充実が求められる
学童保育は、共働き家庭の仕事継続を支える重要な社会インフラです。
しかし、制度や支援体制はまだ十分とは言えず、国や自治体による支援の格差や、民間委託先による質のばらつきが存在します。
今後は、施設整備のスピードアップと、子どもの発達段階に応じたきめ細やかなプログラムの導入が求められます。
さらに、支援員の待遇改善や研修体制の充実も不可欠です。子どもが「楽しい」「また行きたい」と思えるような環境づくりが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 背景 | 共働き世帯増加と核家族化で預け先が不足 |
| ニーズ | 放課後・長期休暇中の子どもの居場所確保 |
| 現状 | 学童保育待機児童1.7万人、地域差あり |
| 支援員課題 | 処遇悪化・人手不足・離職率の高さ |
| 社会的課題 | 制度整備、施設拡充、質の担保が必要 |
小1の壁と放課後時間の両立|子どもの生活と保護者の勤務の現実
小1の壁と放課後時間の両立が直面する現実は、放課後の預かり時間が短い学校と、親のフルタイム勤務のズレから始まります。
例えば、小学1年生は13時半~15時半には下校し、その後の1600時間以上の放課後時間をどう過ごすかが大きな課題です
放課後児童クラブ(学童保育)は受け皿とは言え、閉所時間は平均17~18時と短い上、地域によっては待機児童が多く、希望しても入れない家庭も少なくありません
その結果、親は「鍵っ子」状態で子どもを自宅に残すか、祖父母やファミリーサポートセンターの援助を急きょ頼る状況に追い込まれます
また、子どもが小学生になると、PTA や授業参観などの学校行事が増え、保護者は平日の有給取得や勤務時間の調整を強いられることが頻発します
中には「正社員からパートに切り替えた」「時短が使えず契約職員に変えた」という声も多く、家庭と仕事のバランスを保つために就労形態を根本から見直すケースも増えています
さらに、「小1の壁」は春の入学時だけでなく夏休みや冬休みにも再燃します。長期休暇中は給食がなく、お弁当準備・預かり継続の負担が増すためです
保護者の実際の声(SNSや調査より)
「学童に入れなくて、仕事辞めるしかなかった」
「フルタイムに戻るとお迎えがギリギリ…30分前倒しで調整しました」
対策として取り得る工夫
-
勤務時間の調整:始業・終業のズレを職場と交渉し、時差出勤やフレックス勤務を活用
-
預かり先の多様化:公設・民間学童、ファミサポ、民間託児ルームなどを使い分け
-
長期休暇対策:お弁当配達や延長預かり、地域連携のサービス利用を検討
-
学校行事対応:保護者会やPTA日程を早めに確認し、有給調整や交代体制を整える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 下校時間 | 小1は13時半~15時半 |
| 放課後時間 | 年間約1600時間 |
| 学童の開所 | 17~18時まで、待機あり |
| 仕事とのズレ | フルタイム親はお迎えが難しい |
| 行事・PTA | 平日開催が多く、有給取得必須 |
| 長期休暇 | 給食なし、お弁当と預かりの負担 |
| 対策 | 時差勤務、預け先の工夫、計画的対応 |
共働きでも入れない?学童保育の待機児童問題と対応策
共働き家庭であっても、学童保育に入れないケースは少なくありません。
特に都市部を中心に、定員超過による「待機児童」の問題が深刻化しています。
自治体の利用基準を満たしていても、申込者多数のため入所が叶わないこともあり、保護者の就業継続に大きな支障をきたしています。
学童保育を必要とする理由が明確であっても、選考の結果次第では不承諾となる家庭も多く、年度初めには混乱も起きやすい状況です。
待機児童の増加に対し、各地で学童保育の定員拡充や空き教室の活用が進められています。
また、放課後子ども教室との連携によって、地域単位で受け入れ枠を広げる動きも見られます。
一方で、人手不足が深刻な地域では、支援員の確保が追いつかず、新設を断念するケースもあります。
そのため、支援員の配置基準を緩和し、少人数での運営を認める自治体も増えてきました。
共働き家庭の中には、公設学童に入れなかった場合、やむを得ず民間の学童保育やファミリーサポート、ベビーシッターサービスを利用するケースもあります。
こうしたサービスは利便性が高い一方で、費用負担が大きくなりがちな点が課題です。
また、自治体によっては、夏休みや冬休み期間限定で短期的に利用できる「サマー学童」や、延長預かり対応の新制度を導入するなど、多様な対策が進められています。
これにより、放課後や長期休暇中の預け先としての選択肢が徐々に増えてきています。
保護者側でも、申し込み時に提出する「学童保育を必要とする理由」を工夫して記載することが求められています。
具体的な勤務時間や家庭の状況を明確に書くことで、必要性の高さをアピールしやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題 | 学童保育の定員超過による待機児童の発生 |
| 原因 | 共働き家庭の増加・支援員不足・施設不足 |
| 対応策1 | 定員拡充・空き教室活用・放課後教室との連携 |
| 対応策2 | 支援員配置基準の緩和・柔軟な運営制度 |
| 対応策3 | 民間学童・サマー学童・短期預かりの活用 |
| 保護者の工夫 | 必要性を具体的に伝える申請書の記載 |
民間学童と公立児童クラブの違い|施設の条件や役割を比較
民間学童と公立児童クラブの違い|施設の条件や役割を比較
民間学童と公立児童クラブでは、預かり時間・費用・プログラム・利用条件などに大きな違いがあります。
預かり時間に関しては、公立は18~19時が通常ですが、民間では20時~22時まで延長可能な施設も増えています
利用条件では、公立は共働きやひとり親など就労事情が基準とされますが、民間は子どもの年齢さえ満たしていれば利用可能で、保護者の就労状況に制限がありません 。
費用面では、公立は月額3,000~10,000円程度と抑えられている一方、民間は30,000~70,000円前後のところが多く、さらに送迎や習い事、延長保育など追加料金が発生しやすいです 。
サービス内容は、公立は宿題や自由遊び中心で、スタッフ配置は2名程度で大人数を見守る形式が基本。一方、民間は学習支援・英語やスポーツなどの習い事、送迎サービスや夕食提供など、多彩なプログラムが揃っています 。
運営主体も異なります。公立は自治体または委託法人による公設・公営・公設民営方式ですが、民間は企業・NPO・教育機関が独自の基準で運営し、施設によって質が異なることもあります 。
比較まとめ表
| 項目 | 公立児童クラブ | 民間学童 |
|---|---|---|
| 預かり時間 | ~18〜19時 | ~20〜22時まで延長可 |
| 利用条件 | 共働きなど基準あり | 年齢のみでOK |
| 月謝の目安 | 約3,000〜10,000円 | 約30,000〜70,000円+α |
| プログラム | 自由遊び・宿題中心 | 教育・習い事・送迎・食事 |
| スタッフ体制 | 指導員2名で複数児童 | 多様なスタッフ構成 |
| 運営者 | 自治体(公設・公営など) | 企業・NPO・法人など |
利用時間・送迎体制・保護者の負担の違いとは
利用時間において、公立学童は原則18時〜19時までの預かりが多いのに対し、
民間学童では20時〜22時まで延長可能な施設が増えています。
送迎体制を見ると、公立は保護者または祖父母による迎えが基本で、
公共交通や徒歩が中心ですが、民間学童では学校⇄施設の送迎オプションが充実しており、
悪天候時にも安心です。
保護者の負担に関しては、公立学童は早い閉所時間により、
仕事終わりと迎え時間のズレが常態化し、月に何度も遅刻するケースもあり、
延長保育やシッター利用などで対応が必要とされています 。
一方で民間学童では、長時間預けられる、送迎が任せられるという利点がある反面、
月謝や送迎・延長・食事などオプション費用が高額になりやすいため、
家計への影響は無視できません
| 項目 | 公立学童 | 民間学童 |
|---|---|---|
| 利用時間 | 月〜金 〜18時/一部〜19時 | 延長可能 〜20~22時まで |
| 送迎体制 | 保護者や祖父母が迎え | 施設が送迎、徒歩・交通含む |
| 保護者負担 | 閉所時間に合わせた勤務調整必要、延長費用・手配が発生 | 費用負担増、送迎負担が軽減される |
| 費用目安 | 月額約3,000〜8,000円+おやつ代等 | 月額約20,000〜70,000円+オプション費用 |